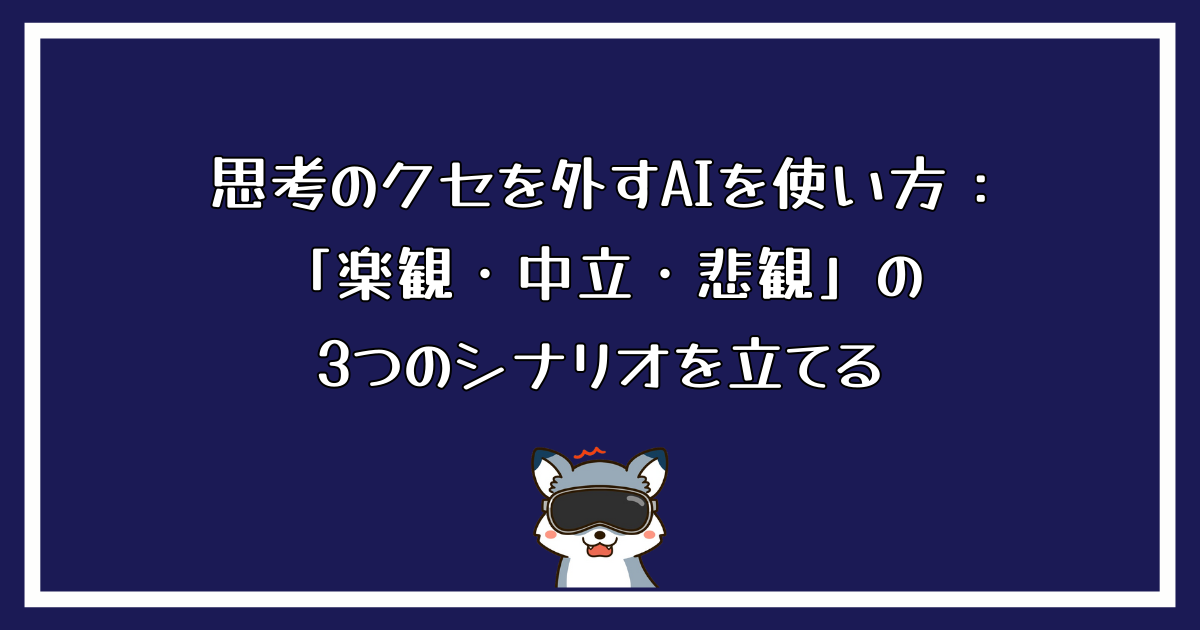
思考のクセを外すAIを使い方 :「楽観・中立・悲観」の3つのシナリオを立てる
はじめに
絶望した、Switch 2のチャット機能を使えるフレンドがいなくて絶望した!全国のなんちゃって絶望先生の皆さん、お世話になっております。yaboです。
私は元々悲観寄りな性格なのですが、悲観的であれ楽観的であれ、得てして人は自分の思考バイアスには気づかないものです。
それは時に大きな見落としを生みます。楽観的すぎるとリスクを過小評価して痛い目を見るし、逆に悲観的すぎるとリスクを過大評価して身動きが取れなくなります。
最近ようやく気づいたのですが、このような自分自身の思考のバイアスを取り除くには、LLMを活用するのがとても有効です。せっかくなのでその具体的な方法を書き留めておこうと思います。
LLMに「3つの視点」から考えさせる
その方法とは、「ある物事について、LLMに楽観・中立・悲観の3つの視点から分析させ、自分の意見がどの視点に最も近いか指摘してもらう」というシンプルなものです。
後になって知りましたが、この手法は「シナリオ・プランニング」と呼ばれ、企業が事業計画を立てる際にもよく使われているものらしいです。
基本的なプロンプトは次のような形になります。
<ある物事>について、私は〇〇と考えています。
この物事について、あなたは楽観・中立・悲観の3つの視点からそれぞれ分析し、その結果を提示してください。
また、私の意見について、その3つの視点のうちどれに近いか考察してください。
この方法を使うと、自分の意見を一般的な立場から見た楽観・中立・悲観のシナリオと並べて俯瞰できるので、思考の偏りやクセを認識することが可能になります。
自分に特定の思考パターンがあることに気付けば、それを意識的に修正することもできるでしょう。
具体的なユースケース
この方法を私が特に頻繁に使うのは、DeepSearch機能と併用して現在の分析から将来を予測する場合です。
例えば先日、上の記事で「QAエンジニアとAI技術の関係」についてGeminiに評価をお願いしたのですが、自分の中では以下のようなバイアスがかかっていることに気づかされました。
- AI技術そのものの将来については楽観的。
- 資本家への経済的影響についても楽観的。
- 労働者への経済的影響については悲観的。
つまり、「AIはあらゆる場面で役立つだろうが、それで儲かるのは資本家だけで、労働者全体としては待遇が悪化する方向に進むのでは?」という考え方をしているわけです(それでも自分がAI驚き屋をしてるのは単純にオモロいからです)。
こうしたバイアスを認識しないまま下手にLLMを使うと、知らず知らずのうちに自分の偏りを強化する材料だけを集めることになってしまいます。いわゆるエコーチェンバーですね。
そのエコーチェンバー化を防ぐためにも、プロンプトテンプレートとして常にLLMに複数の視点を考えさせるのはとても効果的だと思います。
また、自分のキャリアや人生観のような、より個人的なテーマにもこの方法は使えます。
その場合は自分の意見がどの視点に近いかだけでなく、具体的なアクションまで提示してもらうようにすると、実際の意思決定にも役立ちます。
特に最近のLLM、特にChatGPT 4.5は共感力がすでに大半の人間を超えているので(これはマジ)、下手に人間に相談するより的確で妥当なアドバイスをくれることも多々あります。
おわりに
LLMは適切に使えば良き師になり得るような気がしています。実際、最近はChatGPTが自分のカウンセラー、Claudeがプログラミング講師として機能している状況です。
これからもLLMと良い感じの距離感で付き合っていきたいものですね。また新しい使い方を見つけたら紹介したいと思います。ではまた。